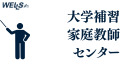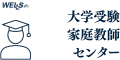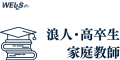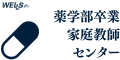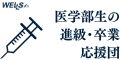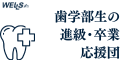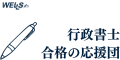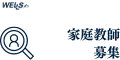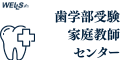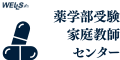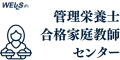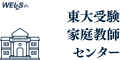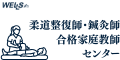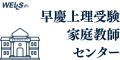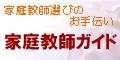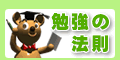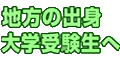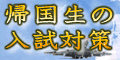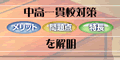過去問を制する者は東大を制す──赤本と向き合う前に知っておきたいこと
図書館の赤本コーナーで見かける光景です
都内の区立図書館では、2 月になると赤本の棚に高校生がずらりと並びます。「とりあえず力試しです」と前年の問題を解き始める姿は毎年の風物詩です。しかし、その後に続く “赤本漂流” もまた恒例行事です。答案に赤ペンで×をつけて終わりにしてしまうと、赤本は 700 g の慰め賞に過ぎません。過去問は「試して落ち込む」ための本ではなく、「合格設計図」を描くための地図帳なのです。
過去問は“敵情視察”のツールです
小まとめ
出題形式・配点・頻出単元を数値化し、“敵” を可視化することが第一歩です。
赤本を手にしたら、最初の 15 分で次の表を作成しましょう。
| 教科 | 大問 | 頻出テーマ | 配点 | 難度メモ |
|---|
これだけで「得点源」「後回し」「必要最低限にとどめる分野」が浮かび上がります。たとえば文 Ⅰ志望なら世界史第 3 問が毎年近代経済史で配点 40 点とわかります。そうであれば夏から重点的に演習を重ねるべきだと判断できます。
早期分析で年間計画に落とし込みます
小まとめ
赤本を最初に“読む”のは 9〜10 月、実際に“解く”のは傾向を把握してからです。
力試しとして本気で解くのは仕上げ期だけで十分です。初見で高得点が出ても安心せず、傾向分析と計画修正に時間を割きましょう。
赤本一冊主義はリスキーです
小まとめ
青・緑・黒・白本も“副読本”として活用し、解説の穴を埋めると効果的です。
- 青本(駿台):別解と採点基準が詳しいです。
- 緑本(Z会):和文英訳など記述例が充実しています。
- 黒本(河合):マーク式のスピード練習に便利です。
11 月以降は品切れが目立ちますので、年内に確保するのが “受験生の常識” です。
過去問が毒になる瞬間もあります
小まとめ
直前に初見で解いて撃沈し、メンタルが崩れるケースを防ぎましょう。
- 解くタイミング:入試 2 か月前までに一周し、以後は再演習に徹します。
- 検証シート:誤答の原因を「知識/思考/時間配分」に分類します。
- 補強プラン:翌週の学習スケジュールへ即座に転記します。
点数そのものではなく、弱点箇所に目を向けることがポイントです。
エピローグ──“赤本漂流”から“赤本航路”へ
最後に、私が担当した受験生 A さんの例をご紹介します。9 月時点で世界史の偏差値は 55 でしたが、赤本の傾向表を作成すると近代経済史が「配点が高いのに曖昧」と判明しました。そこで 12 月までに国際連盟以降の流れを毎週アウトライン暗記し、年明けの東大型プレテストでは世界史 36/40 点を獲得しました。本人は「赤本が“未来の答案用紙”に見えた瞬間、勉強の迷いが消えました」と語っています。
大まとめ
- 敵を可視化する──10 年分の傾向と配点を表にまとめます。
- 年間計画へ反映する──教材と週次タスクを頻出順に並べ替えます。
- 多視点で検証する──複数社の解説で答案力を磨きます。
- サイクル演習を回す──分析→学習→再演習を 2 か月ごとに繰り返します。
- 直前はメンタル管理──点数ではなく弱点修正にのみ注目します。
この 5 ステップを回し切れば、赤本は厚いだけの本ではなく「東大への入場券」に変わります。