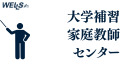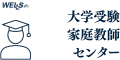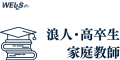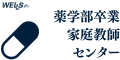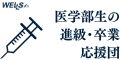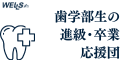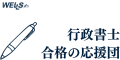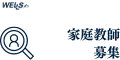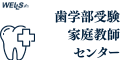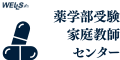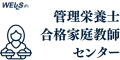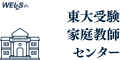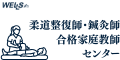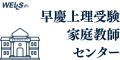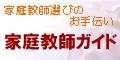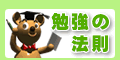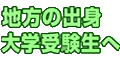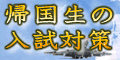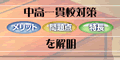東大合格に役立つ「偏差値の壁」と「タイムラグ」攻略法
1 偏差値には段階的な壁がある
- 偏差値40台の人にとっては50、50を超えれば60──というように、得点力が上がるたびに次の壁が現れる。
- 60を越えると65が、65を越えると70が壁になる。70を超えるには、教科ごとの学習精度・時間管理・ミス削減すべてを高いレベルで噛み合わせる必要がある。
- 総合で70を目指すのが難しい場合でも、すべての教科で65以上 をそろえれば合格ラインに届く。苦手教科を残したまま一部の得意教科だけを70台に引き上げても、合計点は安定しにくい。
2 壁を越えるための具体策
- 教科別の得点目標を数値化
- 「数学ⅠAⅡBの大問1と2で満点」など、取るべき問題を先に決める。
- 問題を取捨選択
- 本番では満点を狙わず、合格点に必要な問題だけを確実に解く。
- 時間配分を日頃から測定
- ストップウォッチで演習時間を計り、問題ごとに“平均所要時間”を記録しておく。
- マーク管理法・間違いノートの併用
- × ▽ △ ○ ◎ ☆ の記号で進度と精度を可視化し、弱点を一つずつ潰す。
3 勉強成果には“タイムラグ”がある
- 努力の効果はすぐには成績に反映されず、2か月程度遅れて現れる ことが多い。
- 夏に大幅に勉強したのに9月模試で伸びないのは典型例。10〜11月模試で一気に跳ねるケースがよくある。
- 逆にサボった場合は1か月ほどで成績に影響が出る。下げるのは簡単、戻すにはサボった日数の約3倍 が必要と心得る。
4 上昇タイムラグを味方にする三つの心得
- 焦らない
- 自分を信じる
- いつもどおりのペースを守る
これだけで伸び悩み期のメンタル負荷を大幅に減らせる。
5 下降タイムラグへの警戒
- サボり始めた直後は成績が落ちないため油断しやすい。
- 下降が定着してからのリカバリーには大きな時間コストがかかる。
- 「今日は休む」と決めたら、翌日に必ず倍返し の学習時間を確保するなど、あらかじめルールを決めておく。
6 成果が出ないときは勉強法を点検する
- 成績が長期にわたり停滞する場合は、学習手順が合っていない可能性が高い。
- インプットとアウトプットの比率、間違い直しの精度、時間管理の3点を再確認し、改めるポイントを1つに絞って修正する。
7 「理屈は後から追いかけてくる」現象
- 授業で理解できなかった内容が、翌日ふと分かることがある。
- インプット後に脳内で情報が整理されるまでに時間がかかるため、分からなくてもとりあえず前に進む。
- 復習日を週1回設け、前の週に「分からない」と感じた問題を“再挑戦用リスト”にしておくと定着率が高まる。
8 まとめ:壁とタイムラグを味方に変えるステップ
- 教科別に得点ターゲットを設定し、65→70→75と段階的に狙う。
- マーク管理法と時間計測で学習を可視化し、間違いノートで弱点を残さない。
- 成績が上がらなくても2か月は粘る。サボったら即リカバリープランを組む。
- 分からない箇所は“保留→先へ進む→週末に再挑戦”で脳の整理時間を確保する。
この流れを仕組み化すれば、偏差値の壁を1段ずつ突破し、タイムラグを含めた成績曲線を右肩上がりに整えることができます。